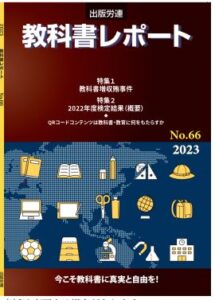
『教科書レポートNo.66/2023年』が、発行となりました。
内容は
特集1 藤井寺市での中学校教科書採択をめぐる「 贈収賄事件」の衝撃
特集2 2022年度実施 高校用・小学校用教科書検定
◇ 学習者用デジタル教科書の現在地と今後
◇ QRコードコンテンツは教科書・教育に何をもたらすか
◇ 2023年の出版労連の教科書価格適正化のとりくみの 成果と課題
◇ 国連から「繰り返し」批判・改善勧告を受けた教科書検定
【チラシ】以下ダウンロード願います↓
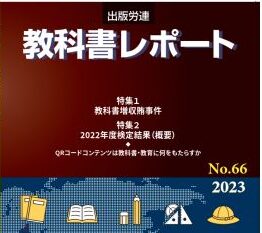
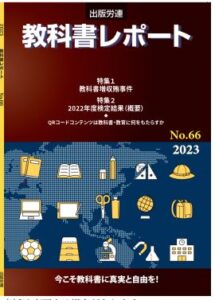
『教科書レポートNo.66/2023年』が、発行となりました。
内容は
特集1 藤井寺市での中学校教科書採択をめぐる「 贈収賄事件」の衝撃
特集2 2022年度実施 高校用・小学校用教科書検定
◇ 学習者用デジタル教科書の現在地と今後
◇ QRコードコンテンツは教科書・教育に何をもたらすか
◇ 2023年の出版労連の教科書価格適正化のとりくみの 成果と課題
◇ 国連から「繰り返し」批判・改善勧告を受けた教科書検定
【チラシ】以下ダウンロード願います↓
2023年4月26日
藤井寺市での教科書採択をめぐる贈収賄問題について【見解】
日本出版労働組合連合会(出版労連)
教科書対策部長 小森浩二
PDF版:230426_kenkai
2021年度、大阪府藤井寺市での中学校教科書採択に関連して大日本図書株式会社(以下「大日本図書」)および同市内の中学校校長(当時。以下「元校長」)による贈収賄事件が引き起こされ、2023年に贈賄側・収賄側の両者に対し、有罪判決が確定した。出版労連教科書対策部は、これを教科書発行にかかわる者を含む産業別単一労働組合(単産)として看過できない問題と認識し、議論をすすめてきた。それをふまえ、以下に見解を表明する。
(問題の概略)
(本件についての見解)
(*)教科書発行者が「採択関係者」を接待し、そうした場で「白表紙本」を見せて意見を聞き、それに対価を支払っていた問題。これを受けて教科書発行者でつくる教科書協会は「教科書発行者行動規範」を策定し、文部科学省の承認を得たうえで各発行者に順守を求めている。
第一に、児童・生徒数の減少=教科書需要数の減少という状況の中で、4年に1度しか採択の機会がなく、しかも広域(共同)採択制度のため、採択結果は「オール・オア・ナッシング」となることである。このため、一度の採択の成否が各教科書発行者の経営状況を大きく左右することにならざるをえず、これが営業活動の過熱の要因となっている。
第二に、教科書採択のプロセスにおいて、現場教員の意見が尊重されていないことである。教科書の調査研究にあたる調査研究委員会(藤井寺市では「教科書選定委員会」)の検討結果を、「教育委員の権限と責任において」行われるとして、教育委員が必ずしも尊重しなくてもよいとする制度に贈収賄が入り込む余地があるといえる。藤井寺市の教育委員会議事録(2020年7月30日臨時教育委員会)でも、学校現場の意見は全く報告されていない。
ただし、こうした制度的要因があるからといって、贈賄が正当化されるわけではないことはいうまでもない。
(再発防止のための提言)
大日本図書は、次期中学校教科書の検定不合格という処分を受けて、現行教科書を継続発行し、これを来年度の教科書採択に供する方針を打ち出した。これにより、採択する教科書がないという事態は避けられたものの、今年の小学校教科書採択を含め、経営状況への否定的な影響は避けがたいだろう。そうした問題はあっても、同社には労働者の雇用を守り、労働条件の不利益変更は避けることを求める。
以上
大日本図書株式会社による教育長等の接待について(見解)
2022.10.24
日本出版労働組合連合会(出版労連)
教科書対策部長
小森浩二
PDF:20221024kenkai
大日本図書株式会社(以下大日本図書)が、教育長らに接待を行っていたことが明らかになった。出版労連教科書対策部は、この問題は以下に述べる観点から軽視できないものであると認識し、ここに見解を表明する。
(経過の概要)
2022年9月30日および10月7日の各メディアの報道によれば、次のような経過であった。
1. 2022年7月1日に、大日本図書営業担当幹部らが、茨城県五霞町(採択地区としては茨城第11地区)の教育長およびその知人の元中学校長と会食し、その代金1人当たり約9,500円を同社が支払い、1,600円の菓子を渡していた。
2. 接待された2名は教育長とその知人の元校長であった。
3. 接待の席上、教科書採択の話は出なかった。
4. 接待を受けた2名は、後日その費用を大日本図書の銀行口座に振り込んだ。
5. 当該教育長は、10月3日に辞職願を町長に提出し、7日付で退職した。
(見解)
1. 大日本図書及び同社が加盟する一般社団法人教科書協会が、9月30日にそれぞれ公表した「お詫び」「令和4年9月30日付の読売新聞報道について」でも述べているように、自ら合意した自主ルール「教科書発行者行動規範」に違反するものである。
2. 教科書採択は、その内容の如何によるべきであって、接待などで左右されてはならない。それにもかかわらず、同様の問題は前出の自主ルール策定後も複数の教科書発行者により、何度か起こっている。こうした問題が、教科書採択制度の構造に根差していることを指摘しなければならない。
3. 教科書無償措置法に基づく義務教育教科書の採択が1964年に施行されて以後、教科書業界では与党や政府高官への献金をはじめ、最近も2016年の「白表紙問題」、教育課題アドバイザー制度といった問題が繰り返され、出版労連とその傘下の教科書労働組合共闘会議(教科書共闘)は、これらの問題を強く批判し、その清算を要求してたたかってきた。今回の問題は、その体質がいまだに払拭されていないことを示すものである。これを機に、教科書業界の体質を根本的に改めるべきである。各発行者に対し、そのための努力を要求するものである。
4. 今回のような問題の再発防止のためには、教科書発行者の自覚が必要であることは当然だが、それに加えて、少なくとも次のような教科書制度の改革が必要である。各発行者の自覚に委ねるだけでは、いずれ再発する可能性は高いと言わなければならない。
(1) 義務教育教科書で行われている現行広域採択制度(共同採択制度)を改め、高等学校同様、学校ごと採択にすること。高等学校では実施しているにもかかわらず、義務教育では不可能であるとの文部科学省の主張は成り立たない。この制度は、4年ごとに「オール・オア・ナッシング」「ウィナー・テイク・オール」という結果をもたらすきわめて不合理な制度である。
(2) 教科書価格を大幅に引き上げて適正化すること。この問題の根本には、児童生徒数の減少と価格の抑制による教科書業界への先行きに対する経営の不安と懸念がある。文部科学省の来年度の概算要求でも、引き上げ率は1.4%にすぎない。文部科学省は物価高騰、特に用紙代の高騰を考慮したとするが、全く不十分である。その意味では今回の問題を引き起こした根源は国家政策にあると言わなければならない。
5. 今回の問題を利用して教科書発行者の正当な営業活動を萎縮させるような動きがあれば、断固反対する。
以上
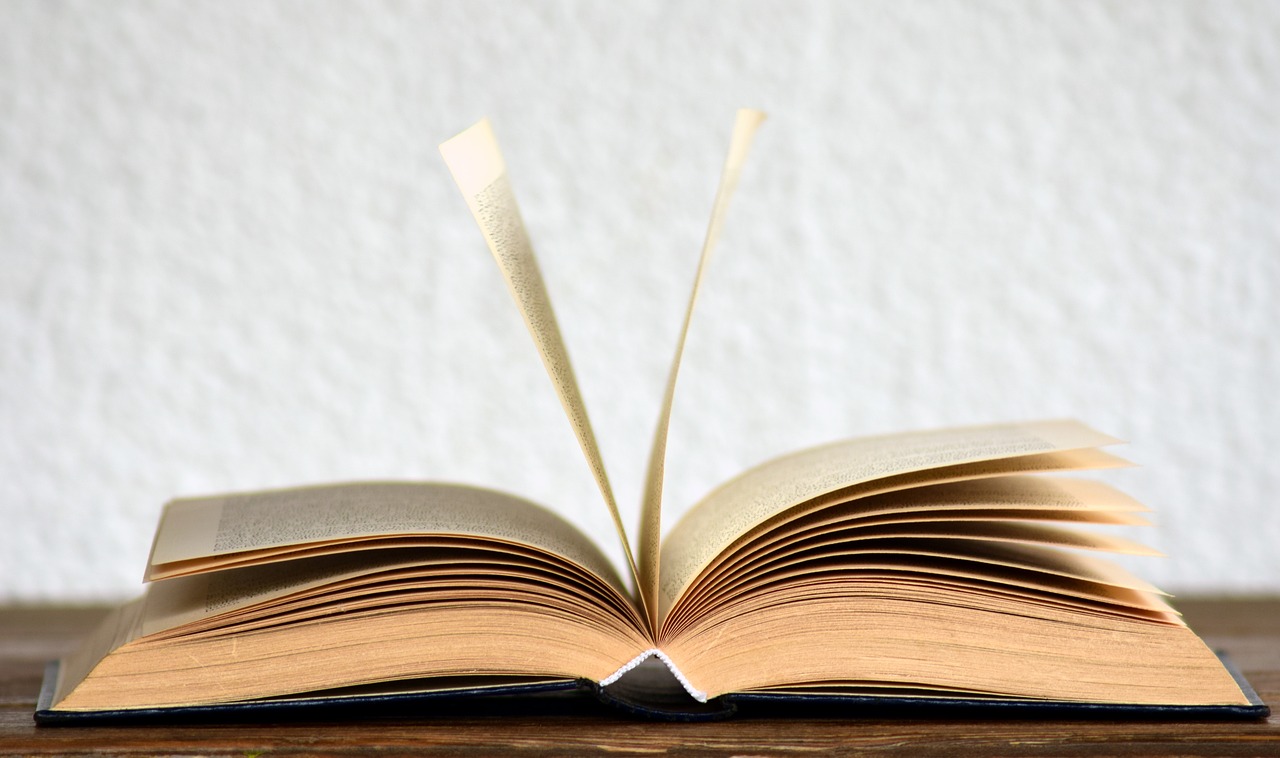
2022年4月22日
日本出版労働組合連合会
教科書対策部
2021年度実施教科書検定結果についての見解
3月29日の教科用図書検定調査審議会総会を経て、2021年度に行われた教科書検定結果が報道解禁となった。出版労連教科書対策部は、これについての見解を表明する。本見解は、各種報道によって現時点で判明しているかぎりのものであり、詳細については、今後刊行する『教科書レポート2022』(No.65)誌上で表明することとする。検定に関する情報は「静ひつな審査環境の確保」を理由に極度に秘匿されており、5月下旬頃になるまで入手困難である。このこと自体不当であり、少なくとも報道解禁と同時に公開することを求めるものである。
1.概要
今回も、全体としては客観的な誤りの修正が最多であった。誤記自体は弁明できないが、誤記が頻発する背景には、各教科書発行者で検定申請の日程に間に合わせるために長時間過密労働が横行していること、その原因は教科書価格があまりにも安いため、必要な人員の確保の困難さがあることを指摘しておきたい。
後述する「国語表現」や,理科で「生物」で検定意見数が突出して多いことと合わせて,検定制度そのものの正当性を揺るがしかねない事例が見られたことは重大である。
「令和書籍」が再申請した中学校社会科歴史的分野『国史』は今回も不合格になった。出版労連としては不合格処分を伴う教科書検定制度には一般的には反対である。しかし『国史』は、その歴史修正主義的・復古主義的内容はもとより、事実誤認や誤記があまりに多く、一般図書としても、まして中学校で使用する教材として不適切なものであり、検定申請するに値しないものであったことを厳しく批判するものである。
2.「従軍慰安婦」「強制連行」「強制労働」
「政府の統一的見解に従っていない」として、「従軍慰安婦」からの「従軍」の削除、アジア太平洋戦争中の植民地とされた朝鮮半島からの労働者の「強制連行」「強制労働」から「強制」を削除させる意見が付けられた。この問題については『教科書レポート2021』で詳述したとおりであるが、該当する検定基準は「閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること」(地理歴史科1-(5))とあり、「最高裁判所の判例」には「軍隊慰安婦」としたものもある(「アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟」判決。2004年11月29日)ことが、2021年5月26日の衆議院文部科学委員会で指摘されている(なお、この質疑では萩生田文部科学大臣(当時)も政府参考人も、この判決を知らないと述べた)。この事実を無視して「政府の統一的な見解」のみを検定に適用したことは、文科省自ら検定基準を歪めて適用した政治的な偏向というほかない。
そもそも「政府の統一的な見解」としての閣議決定自体、この例に見られるとおり決して政治的に公正なものとは限らず、検定基準である「政治や宗教の扱いは、教育基本法第14条(政治教育)及び第15条(宗教教育)の規定に照らして適切かつ公正であり、特定の政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり、それらを非難していたりするところはないこと」(教科用図書検定基準第2章2-(4))を自2ら逸脱して憚らない検定姿勢にも合わせて強く抗議する。一方、このような検定意見に対し、何とか歴史の事実を伝えようとした教科書発行者も複数あり、その著者および編集者の努力は正当に評価されるべきである。
3.領土問題
歴史認識同様、「政府の統一的な見解」を書かせる検定意見が今回もつけられ、竹島は日本の固有の領土である、中国政府との間に領土問題は存在しないという日本政府の主張に基づいた記述に修正された。相手国の主張の紹介すら認めず、日本政府の見解のみを書かせるのでは、ナショナリズムのぶつかり合いにしかならず、領土問題の解決にはつながらないであろう。このような検定は、学習指導要領が示す「主体的・対話的で深い学び」を文部科学省自身が否定しているものというべきである。
4.「国語表現」への文学作品の掲載
2020年度の「現代の国語」での検定で、文学作品(学習指導要領では「文学的な文章」)の掲載をめぐって、ダブルスタンダードというべき検定が行われたが、今回も同様の事態が起こっている。当該ケースは「現代の国語」とは別の教科書発行者であり、検定姿勢が是正されていない。このことは、教科書検定の公正性を揺るがす問題であるので、出版労連としては、引き続き検証と批判を重ね、教科書の自由を守る立場から是正を要求していく所存である。
5.事実を偽る日本政府の国連自由権委員会への回答
国連自由権委員会は、日本政府の第7回定期報告に先立つ事前質問票(ListofIssues)で、教科書について次のように質問した(原文は英語、外務省仮訳には文書番号および日付の記載なし)。
”また、教科書における言及を含む慰安婦問題に係る学生及び一般市民に対 する教育の取組につき詳述するとともに、歴史上の出来事、特に「慰安婦」問題について、同問題への言及の削除を意図して、政府当局が学校の教科書策定に影響を及ぼしているとの申し立てに回答願いたい。”
これに対し日本政府は以下のように回答した(同上。パラグラフ155は略)。
”156教科書検定は、学習指導要領や検定基準に基づき、検定時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして、記述の欠陥を指摘することを基本として実施している。すなわち、教科書検定は、教科用図書検定調査審議会による専門的・学術的な調査審議の結果に基づいて行われ、その結果は、そのまま文部科学大臣が検定の合否の判断に用いており、そのときどきの政府の方針や政策又は政治的意図が介入する余地はない仕組みとなっている。”
これは教科書検定の実態に照らせば事実を偽るものというほかなく、出版労連としては、これを厳しく批判するとともに、自由権委員会に情報提供を行い、教科書検定制度の不当性を国際社会にも訴えていく所存である。
以上
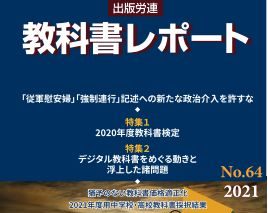
『教科書レポートNo.64/2021年』が、11月30日に発
今号は、特集1「2020年度教科書検定」では、改定された教育
特集2「デジタル教科書をめぐる状況」では、デジタル教科書をめ
この間出版労連がとりくんできた教科書発行自体を危うくする教科
資料として、2020年度高等学校教科書検定内容、2021年度
【チラシ】以下ダウンロード願います↓
https://syuppan.net/wordpress/
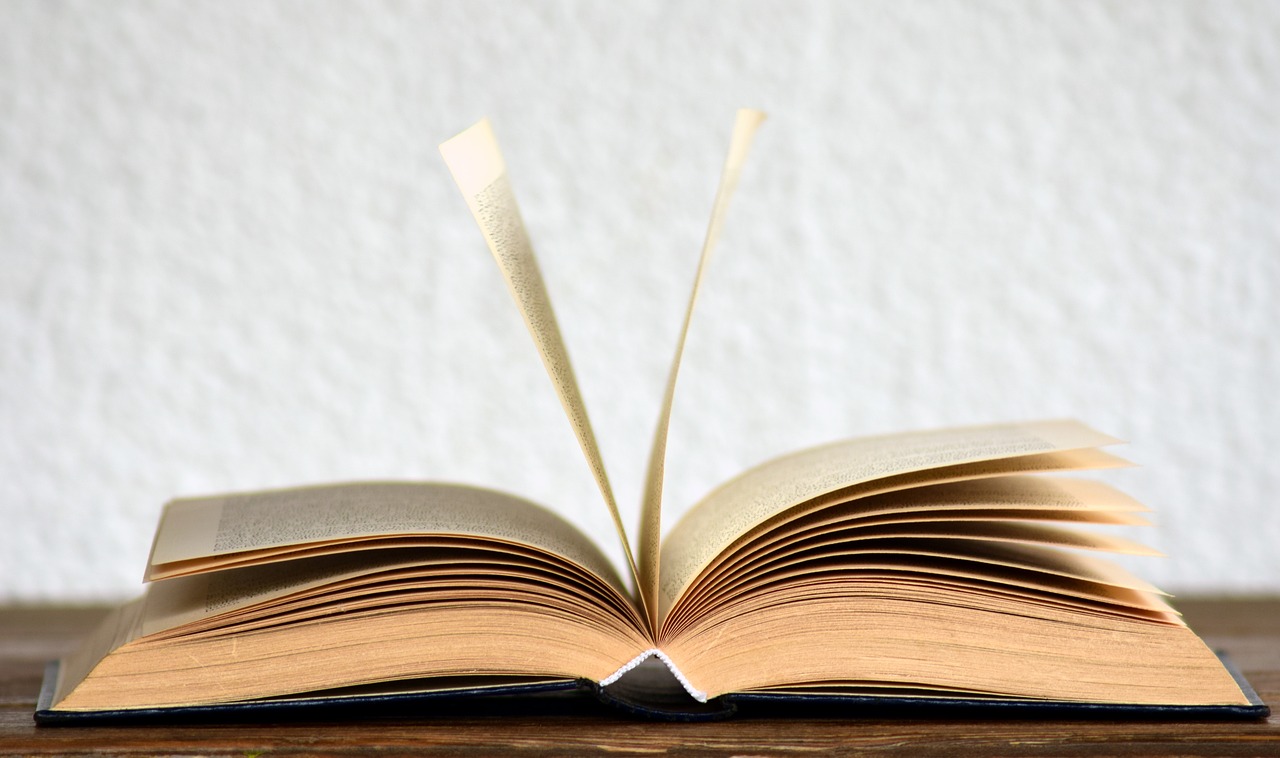
|
教科書記述への権力的介入への抗議文について 教科書対策部は、内閣が閣議決定で「従軍慰安婦」「強制連行」などの用語を変更したことに対し、5月20日付で抗議文を菅首相と萩生田文科相に送付しました。
2021年5月20日
|

「教科書レポート2020」を発行しました。
チラシと申込み書は以下ダウンロードお願いします
↓↓↓
【チラシ】教科書レポート2020
No.63 / 2020年
価格 本体1,100 円+税
〈目次〉
特集1 2019年度 中学校教科書検定
―新学習指導要領初の検定で意見数は全体に減少傾向―
特集2 杉本判決から50年、あらためて家永教科書裁判を考える
「GIGAスクール構想」の現在と今後
過酷さをます教科書職場の実態―検定・採択制度変更、デジタル教
教科書価格適正化のとりくみ
国連自由権委員会をも欺く日本政府の姿勢―教科書検定に「政治的
育鵬社・自由社・令和書籍―執用に検定審製を繰り返す歴史修正主
変わらない日本教科書の内容―教育の営みと無縁の復古主義的徳目
新型コロナウイルス感染問題と教科書
〈資料〉
2019年度 教科書検定内容 -中学校
2020年度用小・中・高校教科書の採択結果
〈資料〉2020年度用小学校・高等学校教科書の採択データ
〈速報〉育鵬社・自由社・日本教科書の採択結果-壊滅的激減の中
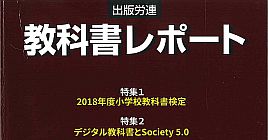
「教科書レポート2019」 が発行されました。
チラシと申込み書は以下ダウンロードお願いします↓
No.62 / 2019 年
本体 1,100 円+税
特集 1 2018 年度 小学校教科書検定
中学校歴史教科書 検定「取り下げ」─という実質的な「不合格」処分特集 2 デジタル教科書と Society5.0
① デジタル教科書をめぐる状況
―デジタル教科書 ・ 教材の可能性と問題点 2019 ―
② Society 5.0 と教育・教科書 ―その背景と影響を考える―
③小学校プログラミング教育の導入の経緯と中身
④デジタル教科書のビューアのこれまでとこれから
・元号と教科書を考える
・出版研究集会第②分科会報告 「教科としての道徳がはじまった」
・学習指導要領と教科書は労働や労働者の権利をどう描いているか
・子どもの権利条約への政府第 4・5 回報告書への総括所見
・教科書対策部ゼミナール「家永教科書裁判とは何だったか?」
2018 年度 教科書検定内容 小学校
教科書採択の公開性・透明性はどうなっているのか?
2019 年度用 小・中・高等学校教科書の採択結果
教科書レポート目次
「教科書レポート2018」第61号を発行しました。
ご注文は、
(1)地元の書店から注文・・・書店さんに「取次店『JRC』扱い」とお伝えください。
(2)出版労連に注文 ↓ ↓ ↓ チラシの注文用紙をお使いください。
《 内 容 》
特集1「転換期の教科書」
1)検定結果
2)教科書検定実施細則
3)デジタル教科書
4)採択をめぐる問題
5)海外との比較
6)教科書制度改善提言作成についてのとりくみ-中間報告
第44回出版研究集会(2017年)報告 どうする、どうなる道徳の教科化
特集2「高校学習指導要領改訂と教科書」
1)改訂の特徴 2)各教科毎の分析 3)高等学校の教科と科目 新旧比較表
前川喜平氏 大いに教科書を語る-教科書検定は公開かつ独立機関で、採択は学校ごとに-
国連人権機関の勧告に強硬姿勢で臨む日本政府
(資料)2017年度教科書検定内容 中学校道徳
(資料)2017年度教科書検定内容 高等学校
2018年度用小学校道徳・高等学校の採択結果
(資料)2018年度用高等学校教科書の採択データ
など