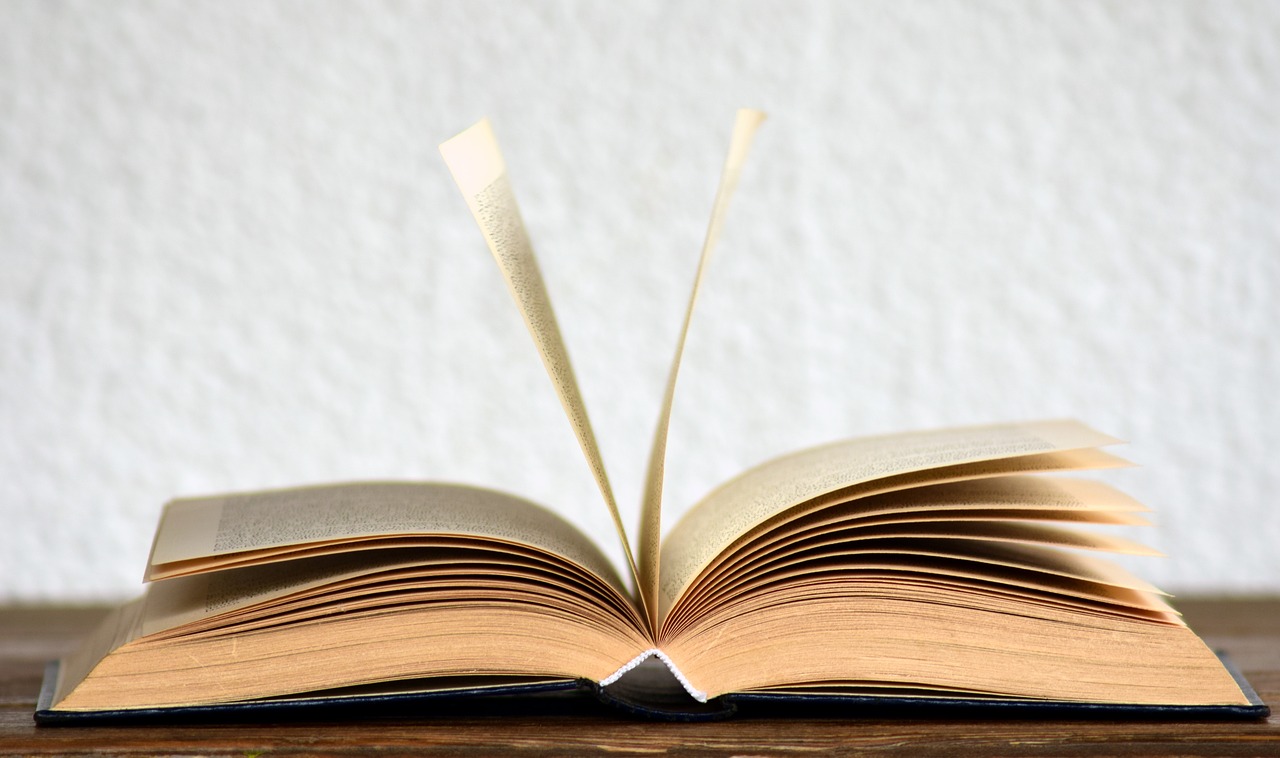第46回出版研究集会 2019年9月27日(金)~ 11月1日(金) 出版産業 新生の時代へ
チラシPDF:20190927_syuppan_kenkyu
全体会 日時:2019年9月27日(金)18:30~20:30/会場:文京区民センター2A会議室
「『ちいさな本』の世界を旅してーブックイベント、地域の本屋、リトルプレス、アーカイブー」
講師:南陀楼(なんだろう)綾(あや)繁(しげ)さん(ライター・編集者、「不忍ブックストリート」代表、「ヒトハコ」編集発行人)
聞き手:樋口 聡(フリーライター/出版・産業対策部事務局長)ほか
→『本とコンピュータ』編集長から不忍ブックストリート、そしてヒトハコ古本市へ。ミニマムでローカルな本と人との出会いを求めて全国を飛び回る編集者、南陀楼綾繁さんをお迎えする。デジタルもアナログも、稀書もミニコミも古本も、コンテンツ産業の全フェーズを観察した経験から出版産業への愛憎を語っていただくとともに、これからの出版界のあり方を議論する。
分科会 時間:18:30~20:30 会場:出版労連会議室
①10/4(金)「Society 5.0 と教育・教科書-その影響は? 教科書・教材はどうなる?-」(仮)
講師・坂本 旬さん(法政大学キャリアデザイン学部教授)
→「Society 5.0」とは何か? 政府は「Society 5.0 の実現」をスローガンに、生産の在り方だけでなく社会の在り方まで大きく変えようとしている。Society 5.0 とは、もともと経済界の要求に端を発した成長戦略だが、文科省をはじめ政府は教育にまで範囲を広げようとしている。そこでは「学びの(公正な)個別最適化」が盛んに謳われ、経済界の求める「人材の育成」がめざされる。
②10/11(金)「コンビニ誌から男の娘(こ)まで-アダルトメディアの行方-」
講師・井戸隆明さん(株式会社パブセンス)
→コンビニ誌の消滅、読者層の高齢化によって紙のアダルトメディアは消滅へと向かっている。そうした中で配信・ダウンロード販売などネットへの移行やコア層をターゲットにした展開など新たな動きも始まっている。今回は、マニア誌を経て会社を設立し各種メディアに携わる井戸さんにアダルトメディアの現状から、井戸さんが情熱を注ぐ「男の娘」をめぐる状況まで語っていただく。
③10/18(金)「出版流通の危機とアマゾン」
講師・高須次郎さん(緑風出版代表/日本出版者協議会相談役)
→「神にも擬せられるほどの力を持つ」といわれるグローバルIT企業GAFAのなかの2強、グーグル、アマゾンに戦いを挑んできた高須次郎氏を招く。バックオーダー中止、直取引の拡大、買い切り制=売れ残りの値引きなどのアマゾンの攻勢。「出版敗戦前夜」ともされる状況で、それを乗り越える道を探る。あわせて取次の物流協業についても深めたい。
④10/25(金)「わかっているようでわかっていない再販制度」
講師・斎藤健司さん(出版再販研究委員会副委員長/金の星社社長)
→今年はゼロから教えます! 再販制が出版産業を支えてきたことは事実。そして現に再販制のもとで産業が回っていることも事実。しかし一方で、出版労働者のなかにも再販制についての知識が十分でなかったり、乏しい人が少なくないことも現実。ひと目でわかる再販商品と非再販商品の見分け方、など再販制を学び直すチャンス。
⑤11/1(金)「図書館利用者のプライバシー保護」
講師・松井正英さん(日本図書館協会・図書館の自由委員会)
→読書は憲法19条(思想及び良心の自由)と密接な関係にあり、図書館利用者のプライバシー保護(貸出履歴の削除など)は重要である。一方、貸出履歴の有効活用の考えや貸出履歴開示の利用者の要望もあり、児童・生徒の貸出履歴と読書指導のあり方の問題もある。これらの問題を、図書館を扱った報道や表現の実例もあげながら考えていく。
*タイトルは変わる場合があります。
【参加費】1,000円(全体会+全分科会の通し券;全体会を除く1分科会のみ参加の場合は500円)
【主 催】出版労連・第46回出版研究集会実行委員会 113-0033東京都文京区本郷4-37-18 いろは本郷ビル2階 TEL03-3816-2911