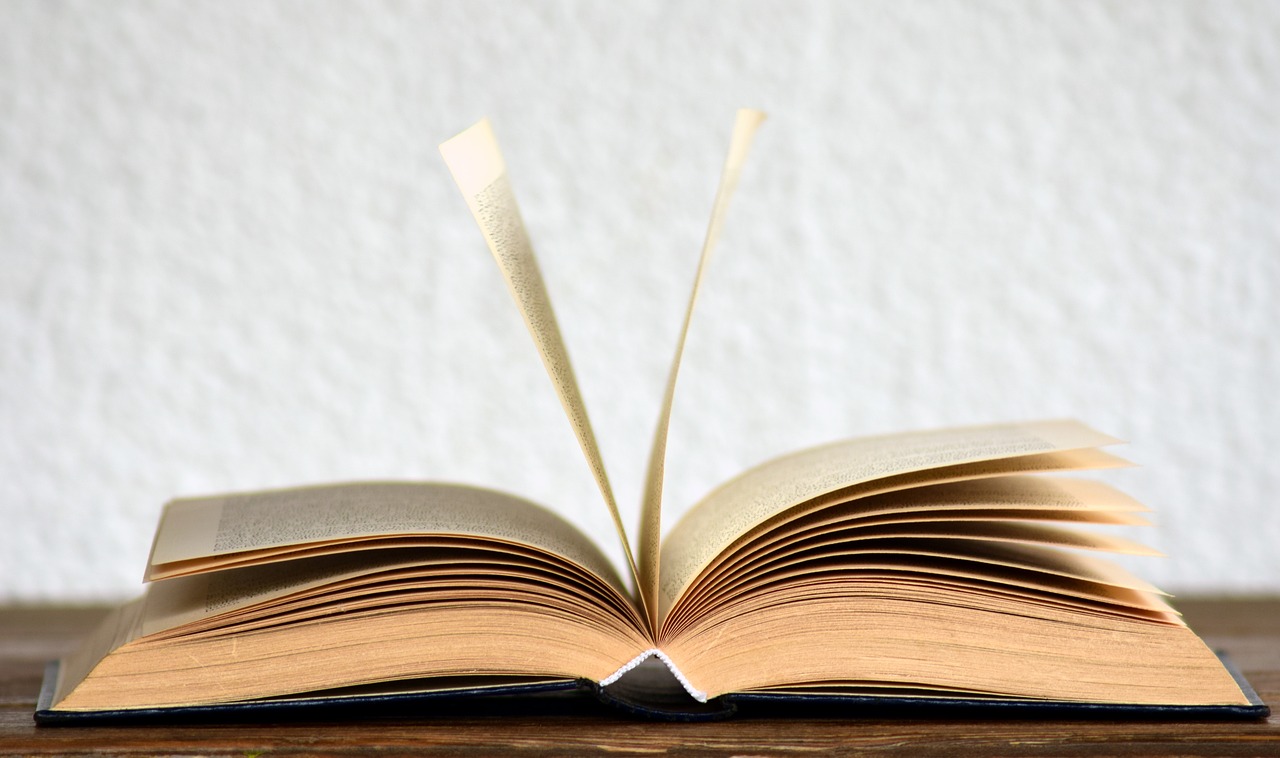ハラスメント根絶特別声明
私たち出版労連は、3年間にわたってハラスメント根絶を重点課題として取り組んできました。ハラスメントは命の問題だからです。経営に対しては、「あらゆるハラスメントの根絶を宣言する」ことを求め、宣言書への社長のサインを求めることを方針にかかげてきました。組合内部においても学習会を重ねてきました。繰り返しハラスメントの問題を取り上げることで、ハラスメントがときに人格を否定する、深刻な人権侵害であるとの問題意識は組合の中に広く浸透してきていると思います。それでもなお、今日もまたハラスメント根絶宣言の特別声明を出さざるをえないこの状況を残念に思います。しかし、この現実を受け止め、諦めることなく私たちの理性と知性とをもって、勇気をもって傍観者を卒業し、声を掛け合い、あらゆるハラスメントに対して毅然とした態度を貫き通しましょう。
「ハラスメントはあってはならないこと」と誰もが認めることであるのに、なぜ繰り返されるのでしょうか。ハラスメントは弱者へ向かいます。すべての人が何らかの立場の優位性を持っています。そのことを、忘れずに他者に向き合うことも大切です。セクシュアルハラスメントの背景には、女性差別が大きく関わっていると言われています。社会的地位が相対的に低い女性はハラスメント被害に遭いやすいのです。同じように、雇用の不安定な契約社員や派遣社員も職場における力学上弱い立場にあるがため、パワーハラスメントの被害に遭いやすいことが指摘されています。ハラスメントを根絶するためには、ハラスメントが起きやすい土壌を一掃することも求められるのです。
労働者の待遇差の改善、雇用の安定、さらに女性やLGBTに対する差別的取扱いの撤廃など、これまでの組合の要求ととりくみを、絶え間なく強力に押し進めていくことが、ハラスメント根絶の一歩となります。
コロナ禍の中、人と人との接触が極端に減っています。社会の前提が覆りました。組合活動も縮小せざるを得ない状況ですが、工夫を重ね、試行錯誤しながら新しい進め方を実践し始めています。一方、経済活動の縮小に伴い雇用関係は不安定さを増してきています。在宅勤務やリモートワークの緊急導入など、働く場や働き方が大きく変容しているいま、従来のハラスメントに加え、周囲が気付きにくいハラスメント、いままでとは違うハラスメントが発生しやすい状況だと推測されます。こんなときだからこそ、いつも以上に周囲に目を配り、ハラスメントの種を蒔かれないよう、ハラスメントの芽を摘んでいく細やかな行動が組合に求められているのです。ハラスメントは人を孤立させたり、離職や、命の危機へ追いつめることもある深刻な人権侵害です。そのことを常に胸におきつつ、コロナ禍による自粛によってハラスメントを見過ごすことのないよう、みんなで協力し合いましょう。
2020年8月27日
日本出版労働組合連合会
第135回定期大会