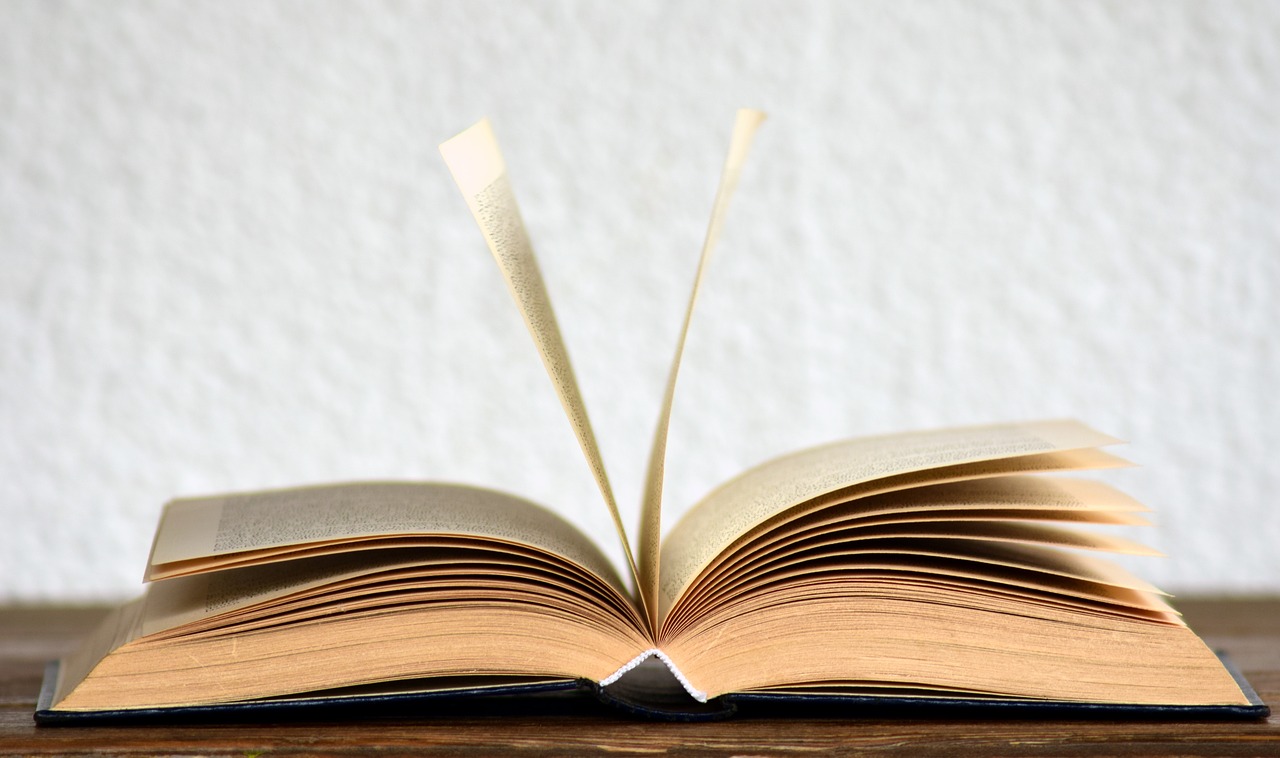第 137 回定期大会特別声明
いまこそ改憲の動きに抗して、言論・出版・表現の自由を守りぬこう
昨今、言論・表現の自由を脅かすさまざまな動きが強まっています。例えば 2020 年 9 月、国から
独立した公的な機関である日本学術会議が推薦した会員候補のうち、6 名の任命を政府が拒否した
ことは、言論・表現、そして学問の自由を脅かす行為だといえます。また、国会審議を軽視して創
設が進められ、2021 年 9 月に設置が予定されているデジタル庁も、個人の自由やプライバシーの侵
害が危惧されます。さらに 2021 年 6 月に成立した改正国民投票法は、CM 規制や最低投票率の基準
がないなど、憲法改正の手続きとしては欠陥だらけの法律であるにもかかわらず、成立してから問
題点は議論する、として採決されてしまいました。同年 6 月には重要土地調査規制法が、衆参あわ
せても 20 数時間という短い審議時間で充分な議論を経ず、専門家の意見を聞かないなかで可決・成
立しました。基地が集中する沖縄はもちろん、米軍横田基地のある東京都福生市など、米軍・自衛
隊基地を抱える全国の市町村で、政府による恣意的な運用を懸念する声があがっています。
国会の動き以外にも、東京や大阪の「表現の不自由展」の開催が、妨害活動により危ぶまれてい
ます。そして、東京五輪・パラリンピックの取材のため来日した記者の行動を、大会組織委員会が
GPS で追跡しようとしていることに対して、海外のメディアから批判の声があがりました。さらに
「美々卯スラップ訴訟」のように、言論に対する恫喝目的で提議される高額訴訟である SLAPP も起
こっています。
また、教科書に関しては、2021 年 5 月に内閣が閣議決定で「従軍慰安婦」などを「慰安婦」に、
「強制連行」「強制労働」を「徴用」に、日本の戦争加害責任がなかったかのように変更しました。
小中社会科と高校地歴・公民の教科書記述を閣議決定どおりにしろというのがねらいです。教科書
記述の変更には「訂正申請」という手続きが必要で、文部科学省は該当する教科書発行者に対し異
例の「説明会」を開き、訂正申請のスケジュールを示しました。これは教科書に対する事実上の圧
力にほかなりません。
一方、マスメディアではいま、同調圧力と忖度のもとで自由な発言や表現が難しくなっています。
フェイクニュースや大手マスコミの一部も加担する権力におもねった報道、また SNS を利用したバ
ッシング、ヘイト書き込みなどに対し、それらの対極にある、ジャーナリズム本来の、権力を監視
する役割が重要性を増しています。しかし、ミャンマー軍事政権による民衆に対する不当拘束や、
香港での民主化を求める声に対する暴力的な取り締まりなどの、海外の言論の自由に対する規制の
動きも、わたしたちにとって他人事ではなく、決して楽観することはできません。
いま、憲法改正を進める動きが強まっています。2012 年の自民党改憲草案は、言論・出版・表現
の自由を保障する日本国憲法 21 条に第 2 項を加え、「公益及び公の秩序を害することを目的とする」
活動は認めないとしています。このような憲法改正が、出版で働くものに重大な危機をもたらすことは
明白です。
わたしたちは、言論・出版・表現の自由を守るために、憲法 21 条を含む改憲に反対します。そし
て、あらゆる取材妨害に反対し、取材の自由を求めるとりくみを行います。また、ヘイトスピーチ
や暴力的な威圧行為などの、差別と暴力を根絶するとりくみを行います。
以上
2021 年 7 月 16 日
日本出版労働組合連合会 中央執行委員会
クリック↓
2103特別声明「言論・表現の自由と憲法」