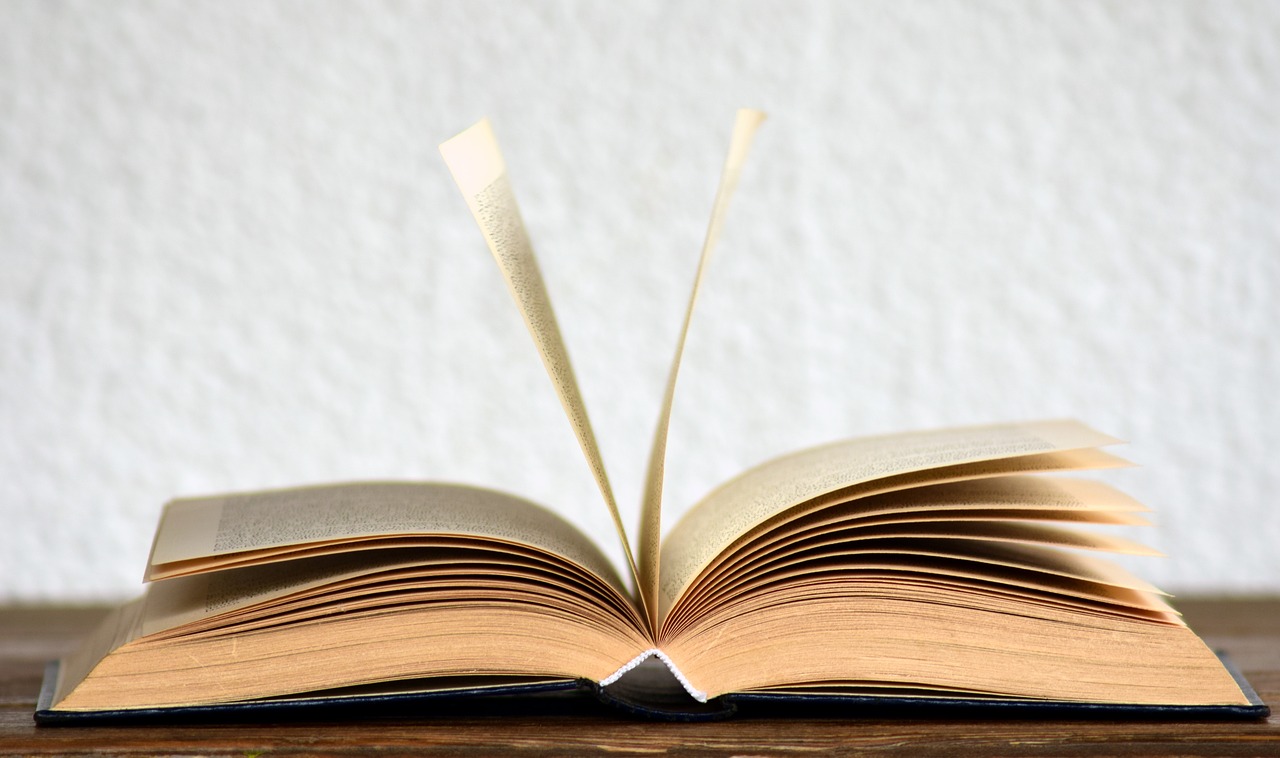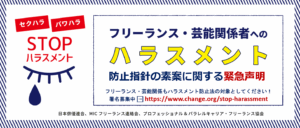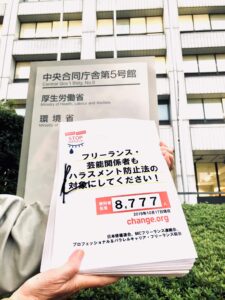新型コロナウイルス感染症対応に関する申し入れの呼びかけ
2020年3月17日/出版労連書記局
出版労連は2月20日(3月5日に項目追加)、新型コロナウイルス感染症対応について、正規・非正規を問わない適切な対応(必要な場合の自宅待機等と就業扱い〈賃金保障〉)を会社に申し入れる際のポイント(後掲)を発表したところですが、出版関連産業では多くのフリーランスが働いていることから、当面、いわゆる「常駐フリー」に関わる課題を中心に、社員(雇用労働者)に準じた対応を会社に要請する際のポイントを追加発表します。
【申し入れ内容例】
会社は、いわゆる「常駐フリー」(週ないし月何日かを問わず出版社等に通って編集、校正その他の業務に委託契約等で従事している人)に対し、社員に準じた配慮をするよう申し入れます。
1 出版社等は、事業場の管理者として、社員だけでなく同じ場で働く常駐フリーに対しても安全配慮義務があることに留意し、感染防止・健康確保のための会社施策等(消毒、時差出勤、自宅待機その他)の情報を常駐フリーにも速やかに周知すること。
2 出版社等がフリーランスと直接契約を交わしている場合には、契約を打ち切ることなく継続し、新型コロナ感染症対応に関わる休業、自宅待機、時差出勤、在宅就業(テレワーク)等に際し、社員への扱いに準じ、通常時と同じ額の支払いを維持すること。
3 フリーランスがプロダクション等と契約し出版社等に出向いて仕事をしている(出版社等とフリーランスとの間に直接の契約関係がない)場合には、出版社等からプロダクション等へ、「当社で働くフリーランスとの契約を維持し、通常時と同じ額の支払いを続けること」を要請すること。前提として、出版社等はプロダクション等との契約を維持し、通常時と同じ額の支払いを続けること。
4 経済産業大臣、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長が3月10日に発出した新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者への要請を踏まえ、「常駐フリー」以外のフリーランスへの発注等についても、できる限りの配慮を行うこと。
<参考>
●新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金[厚労省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
☆リーフレット(PDF)<3月31日まで>
☆リーフレット(PDF)<4月以降>
☆リーフレット(PDF)<2/27~6/30版> *最新*
●新型コロナウイルス感染症により影響を受けている個人事業主・フリーランスとの取引について、発注事業者に要請します[経産省・厚労省・公取委発 2020年3月10日付](PDF)
【申し入れ内容例/2020年2月20日付】
会社は、正規、非正規の雇用形態を問わず、新型コロナウイルス感染症について以下の措置を講じるよう申し入れる。
1 会社は、厚生労働省の示す方針を元に新型コロナウイルス感染症の予防について適切な措置を講ずること。
2 会社は、本人または同居の家族とも、厚生労働省の示す新型コロナウイルス感染症の疑いのある症状が出た場合、自宅待機とするなど適切な措置を講ずること。
3 会社は、本人または同居の家族に新型コロナウイルス感染症の診断が出た場合、治癒するまでは出社を停止させること。
4 自宅待機などの期間、および発病から出社日までの平日の出社停止期間は、就業扱いとすること。
5 罹患について本人の不利益となる取り扱いをしないこと。
6 会社は、上記に限らず、厚生労働省の方針、状況の変化に応じた措置を、組合と協議の上、迅速に講じること。
【追加しての申し入れ内容例/2020年3月5日付】
1 会社は、学校・学童保育・幼稚園・保育園の休業にともなって必要となる育児時短については、必要時間を有給で保障すること。
2 上記に限らず、個別の状況に応じた措置を、組合と協議の上、迅速に講じること。
<参考>
・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援に関して[厚労省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
☆リーフレット(PDF)<2/27~6/30版> *最新*