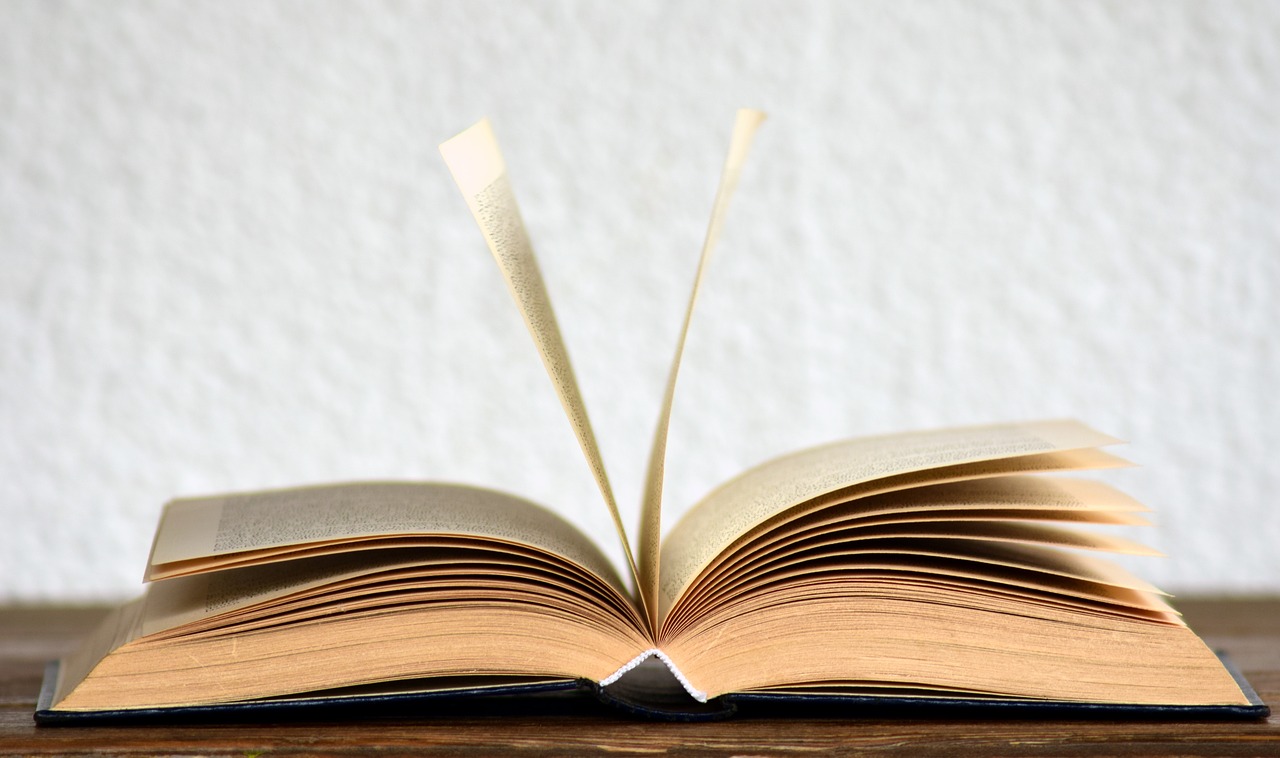特別声明 取次労働者の雇用確保に向けて力を合わせよう
PDF:200827特別声明・出版流通
新型コロナウイルスの感染拡大は、出版産業にも多大な影響を及ぼしています。4月の緊急事態宣言発令下では、書店の休業・時短営業、ネット書店での入荷制限などが行われ、出版流通にも大きな混乱が生じました。このようななかでも、書籍や雑誌の流通は何とか機能しつづけています。それを支えているのは、出版流通の現場で働くたくさんの労働者です。
しかし、かねて出版流通の現場には、低賃金と劣悪な労働条件、不安定な雇用が広がっています。出版情報関連ユニオンに加入した、大手取次の現場で働く非正規労働者は、ほとんどが都県の最低賃金で働いており、ダブルワークで生活をつないでいる仲間もいます。現場ではしばしばパワハラ・セクハラ事案も起きています。
そのようななかで組合員たちは、長年の粘り強いとりくみによって、雇用契約期間の延長、社会保険への加入、ハラスメント根絶宣言への社長署名、パワハラを伴う退職強要の撤回などを勝ち取ってきました。私たち出版労連は、取次非正規労働者の権利向上を、産業新生の課題としても位置づけ、出版関連産業全体に向けてとりくみを呼びかけてきました。
新型コロナウイルスの感染が拡大するなかでも、在宅勤務とは無縁で、会社によるマスク配布さえ不充分ななかで、彼ら・彼女らは感染のリスクを冒して働きつづけ、出版流通を支えています。生活できる賃金、安心して働ける職場環境を実現するために、いっそう力を合わせていくことを、あらためて呼びかけます。
2019年4月、日販とトーハンは、物流拠点の「協業化」(統廃合)を進めていくと発表しました。その「第1弾」として、トーハン・加須事業所(東京ロジスティックスセンター)で行われている雑誌返品業務を、2021年3月までに日販・蓮田事業所(出版共同流通・蓮田センター)にすべて移すとされています。
この加須事業所には、出版情報関連ユニオンの組合員が10人います。加須事業所にはこうした非正規労働者が600人ほど働いていると見られ、今回の統廃合はその雇用と生活に直結します。また、組合員のいる日販・王子流通センターをはじめ、他の事業所でも今後、「協業化」を進めていくと発表されています。
組合員たちは、団体交渉で経営側の雇用責任を確認するとともに、雇用契約の無期転換のいっせい申し込み(勤続5年未満の者を含む約40名、全員受理)を行うなど、積極的にとりくみを進めています。自分自身の生活に不安を抱えながらも、同じ現場で働くすべての仲間の雇用を守るために尽力しています。
現場で汗を流して働く労働者たちに、これ以上の雇用・労働条件悪化を強いることは許されません。私たちは、取次労働者の雇用と生活を守り、賃金・労働条件を改善するために、いっそう力をそそぐとともに、引き続き、出版関連産業に携わるすべての人々に協力を呼びかけます。
以上
2020 年 8 月 27 日
日本出版労働組合連合会
第 135 回定期大会